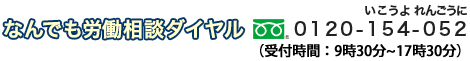なんでも労働相談Q&A
Q. 現在、私の勤めている職場では、雇用形態が多岐にわたっています。その中でパート職員については、時間給が最低賃金であり、最近の物価高騰もあり、1円でも多く上げて欲しいという要望があります。最低賃金については、年々、見直しされているようであるが、全国統一ではないのですか?併せて、その決定プロセスを知りたいのです。会社は、昨年から最低賃金が上った分について、勤務シフトを減らし、結果として月の手取りは全く変わらないように調整しています。自分たちの給料を上げるにはどのような方法があるかアドバイスをお願いします。
A. 地域別最低賃金については各都道府県の地方最低賃金審議会において、公労使を代表する委員によって協議し金額が決定されることになっており、都道府県によって金額が違います。
最低賃金改定後に「勤務時間を減らす」ことで、会社が人件費総額を抑えるケースは見受けられます。労働契約に基づいた範囲内での就業時間の変更は法律違反ではありませんが、労働者にとって望むべき状況ではありません。
現在、国も業務改善助成金制度など最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業などを行っています。同僚の方と一緒になって、制度の活用など会社の認識を確認され、話し合いをされることをおすすめします。
さらに自分たちの賃金を含め、労働条件の向上を求める手段として、労働組合の結成を考えてみてはいかがでしょうか?
Q.入社面接時には、盆正月の休みがあると確認の上入社しました。入社5年目まで夏季休暇は3~4日程度ありましたが、昨年は1日だけで今年の夏季休暇は無しと言われ、全社員統一で2日間有給を取得するよう指示されました。就業規則は途中で変更されているようで、変更部分は分からないが、現状、休日は①1月1日②その他会社が定める日となっているという理由で、昨年から夏季休暇は1日に変更され、今年は無し。入社時の雇用契約に記載はないが、入社から5年間夏季休暇はもらえていたので慣習と感じていました。夏季休暇として有給取得の指示の上、2日間という制限に憤りを感じるが、これは会社の正当な権利になりますか?
A. 労働契約は口頭でも成立する諾成契約です。契約すると、その労働条件等のついても、契約時に双方の合意があれば成立します。相談では労働契約を締結した時点に「盆正月の休みがある」と確認されていることから、具体的な日や日数の発言無くとも、会社は「盆正月休み」を与えなければなりません5年目まで夏季休暇が3~4日程度あったとのこと。相談内容から、夏季休暇は特別休日(年次有給休暇ではない)であると推察しますので、これについて就業規則に記載されていなければなりません。
就業規則に具体的な期日や日数が記載されていなくとも、この夏季休暇は慣習上の休日であると考えるのが一般的であり、この時期に休むことが暗黙の規則として取り扱われるものと考えます。相談には「就業規則は「途中変更されている様で変更箇所は分からない」とのことですが、就業規則には周知義務があり、会社は就業規則を作成・変更した場合、従業員に周知しなければなりませんし、変更した就業規則は労働基準監督署に届け出なければなりません。これらの義務を果たしていない就業規則は無効となる場合があります。
昨年は夏季休暇が1日に、今年は無しになってしまったとのこと。労働条件を変更するに当てっては、契約者同士個人個人の了解を得る、就業規則の変更などで可能ですが、労働者に不利な変更については、丁寧な説明と不利益度合いにより労働者個人の同意を必要とする場合があります。
相談者は夏季休暇があることを前提に労働契約を締結していますので、この変更は大きな労働条件の変更と考えられ、相談者の同意なく労働条件が変更されることは不利益変更に当たる可能性が高いものと考えます。
Q. 10人以下の小規模な事業所で働いています。就業規則は無く、休暇について記載等もされていませんが、先日急に8月中旬に2日間休みにすると言われました。社員は有給休暇となりますが、パートは無給だそうです。就業規則等に記載が無いのにそのような扱いはおかしいと思います。また、年始に示された年間スケジュールでは、その日は出勤日となっていました。急に休みとされた場合は会社都合の休みと捉えて休業手当を要求することは出来るのでしょうか。
A. 2日間の休みについて会社は社員を有給にするとのことですが、本来この2日間は出勤日であったので、
①会社は労働義務を免除して有給にする
②会社が年次有給休暇の取得(計画年休か5日の時季指定)とする
の2通りどちらかの対応が行われると考えられます。
会社が社員を有給にしたにも関わらず、パートを無給とする場合、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間における不合理な待遇差である可能性が高く、同一労働同一賃金の観点からパートも同様に有給とすべきと考えます。ただし不合理な待遇差であるか否かは行政もしくは司法による判断が必要となるので、労働局の総合労働相談コーナーへご相談ください。
5日以上の分の年次有給休暇については、会社と労働者代表の協定で取得日を時季指定することが出来ます。これは会社と労働者との協定ですから拒否できません。ただし残存する年次有給休暇が5日以下の場合に会社は、特別休暇の付与(同一労働同一賃金から100%を求める)、休業手当の支払い(平均賃金の60%)、または有給休暇の前倒し付与といった対応をする必要があります。
どの場合でも2日の休みが社員にとってどんな理由によるのか確認する必要があります。その上で、休業ならば100%の賃金支払いを求めてください。
計画年休なら年次有給休暇の取得、計画年休であるが年次有給休暇の付与が5日以下の場合は、特別休暇の付与、休業手当の支払い、または有給休暇の前倒し付与を求めてください。
Q. 職場の熱中症対策が不十分です。倉庫業ですが、小さい窓しか無く、シーリングファンもありますが、温風しか回らず全く涼しくありません。先日の室内気温は37.9℃でした。日によっては39℃にもなります。以前、会社に相談しましたが、自分で管理してくださいと言われました。従業員の半分くらいが、空調服を着用していますが、あまり効果はないと思います。会社の対応に問題は無いのでしょうか。
A. 職場の気温に関する法規則は、主に「事務所衛生基準規則」「安全衛生法」で定められています。事務所衛生基準規則では、冷暖房設備がある事務所では、事業者に室温18℃以上28℃以下に保つよう努めることを求めています。また、労働安全衛生法では、熱中症のリスクが高い作業環境においては、事業者に熱中症対策を講じることを義務付けています。
職場の対策として、WBGT(Wet Bulb Globe Temperature・温球黒球温度)を活用することが勧められています。
WBGT値は「暑さ指数」ともいい、熱中症のリスクが判断できます。気温だけでなく、湿度や太陽から反射した熱も考慮した値です。温度によりWBGT値のリスク区分があり、31℃以上は危険とされています。さらに33℃以上は、安静が求められています。
今年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則では、現場における対応として「熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けされる」としています。対象となるのは、「WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業となっています。上記を参考に、職場の実態について改善の必要性を伝え、同僚の方と一緒に会社と話し合われることが必要と考えます。
職場の対応が進まない場合は、勤務地を管轄する労働基準監督署内の総合労働相談コーナーにご相談する方法もあります。
その際には職場環境の実態が分かるメモや記録を準備することをお勧めします。
会社が労働者の意見を軽視するようでしたら、その旨もお伝えください。
Q. 契約社員として働いています。正社員と同等の仕事量と職務内容なのに賞与が1ヶ月にも満たない金額です。他の契約社員の人たちも同じです。10年以上勤務していても、契約社員の賞与は変わりません。会社は契約社員の賞与について、見直しなどはしないものでしょうか?
A. ご相談は、均衡・均等待遇(同一労働・同一賃金)の観点からの疑問と受け止めます。パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律)が施行され、「通常の労働者」(いわゆる正社員)と、パートタイム(短時間)労働者、有期雇用労働者などの非正規労働者との不合理な待遇差や差別的取り扱いが禁止されました。
事業主が、雇用する短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で待遇差を設ける場合
(1)職務内容(業務の内容+責任の程度)
(2)職務内容・配置変更の範囲
(3)その他の事情の内容を考慮して個々の待遇ごとにその性質・目的に照して不合理と認められるものであってはなりません。
厚労省の策定した同一労働同一賃金ガイドラインは、賞与について「ボーナス(賞与)であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。」としています。このガイドラインに沿うならば、正社員と契約社員の貢献が同一ならば、ボーナスは同額でなければならないということです。
そのことを踏まえて、会社が同額にしているのは、会社は「貢献は同一とみなしていない。」という判断であり、その経緯を説明することができるはずです。お勤め先には労働組合があるようですが、契約社員の方々は組合員になっていますか?労使での団体交渉で従業員の労働条件決めているはずですので、労働組合に尋ねられることをお勧めします。
Q. 午前と午後で違う施設に移動して勤務することがります。午前業務が9時開始で12時半~13時頃終了し、後片付けをし、電車で午後業務の施設の最寄り駅へ移動、お昼休憩を取って15時から午後の業務を開始し、18時半~19時終業という場合が多いです。15時からと言っても、14時35分頃には施設に入って準備をし、15時から開始できるようにしなければなりません。朝も、8時35分頃施設に入って9時の始業開始に間に合うよう準備しています。この基準時間は、勤務時間に含まれていません。移動時間は休憩時間に含まれるのでしょうか?お昼休みが30分しか取れないので勤務変更を願い出ましたが、みんなこれでやってくれているから頑張ってほしいと言われました。勤務時間とされている時間が実際働いている時間と合っていないような気がしています。始業前の準備時間および午前と午後の移動時間は勤務時間に含まれないのでしょうか?
A. 今の福祉施設に入社される際に労働時間について雇用契約書か、雇用通知書で確認していると思います。その中で労働時間はどうなっているのでしょうか?休憩時間も記載されていると思います。そこに書かれている内容が基本的な勤務体系です。
休憩時間は無給ですが、その時間に働けば時間外労働となり賃金が支払われなければなりません。始業前の準備時間は上司(会社)の指示で行っているとすれば、労働時間となり時間外手当の支給対象になります。2ヵ所の職場で働いているとのことですが、本来2ヵ所勤務を雇用契約書の中で明示されていないとすれば問題なのですが、上司に指示で二つの職場で働いているわけですから、移動時間があるとすれば労働時間となります。
休憩時間とは、労働者が労働から離脱することを保証されている時間であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱われます。まずは、職場で同じようにお困りの同僚の方と一緒に話し合いをされることをお勧めいたします。職場で労働組合を作り、会社と交渉することもご検討ください。
Q. アルバイトを辞めて、現在は新社会人として働いています。アルバイトを退職するとき有給休暇の残日数が10日分あったので有給休暇取得の申請をしましたが給与に反映されていませんでした。退職時に店長から有給休暇取得について何の説明もありませんでしたので、アルバイト先の本部へ連絡したところ、「給与支払い日が過ぎているため対応できない」との回答得を得ました。しかしながら、他店舗では事前に店長経由で申請し、有給休暇を取得しているとの情報があります。現状において有給休暇取得分の未払いについて請求することは出来るのでしょうか?
A. 年次有給休暇は一定期間勤続した労働者に対し、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇です。法律により定められた労働者の権利ですので、会社は労働者が希望した日に取得させる義務を負っています。
年次有給休暇の取得を申請していたにもかかわらず、店長が年次有給休暇として取り扱っていなかった場合、これは「賃金の未払い」ということになります。賃金未払いであるのにもかかわらず、本部から「給与支給日が過ぎているため対応できない」という回答があったとすれば、これは由々しき問題です。賃金未払いの消滅時効は5年(当面の間3年)とされているので、相談者にはその賃金支払いを求める権利があります。
相手に対して何かを訴えるには、訴える側がその証拠を提示する義務があります。今回は年次有給休暇の取得を申請したやりとりがそれにあたるとものと考えられます。また、勤務した実績と支払われた賃金により、実際に年次有給休暇を取得した分が支払われていないことを証明することが出来ます。これらの証拠を揃え、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ、会社に未払い分について支払うよう指導していただくようご相談してください。
Q. 正社員として働いています。賃金は基本給+みなし残業代(20時間分)が会社から支払われています。今までは残業ゼロでもみなし残業代が支払われ、会社から何も言われませんでした。しかし、今月からみなし残業の20時間分も所定労働時間とプラスで必ず働くよう指示がありました。個人的に通勤に往復3時間以上かかっており、これ以上の労働が厳しく、その旨を会社に伝えると会社からの指示なので従うよう言われました。調べると、会社はみなし残業分の労働を強制できないなど色々な情報が出てくるのですが、実際はどうなのか教えて欲しい。
A. 固定残業代(みなし残業代)制度は、あらかじめ決まった時間分の残業代を給与に含めて支払う制度です。
しかし、残業の強制は認められません。この制度にはいくつかの厳格な運用条件があり、会社は社員に残業を強制したり、固定残業代分の残業をしないことを理由に賃金を減額したりすることは出来ないことになっています。固定残業代というのは、あくまでも一定時間残業をしたものとみなして、その賃金(残業代)を支払うための制度であり、労働者が必ずその時間分働かなくてはならないという義務は生じません。
固定残業代は、「実際に残業しなくても支払う」というのが原則であり、「たとえ実際に残業しなくても」支払われるべきものなのです。したがって、プラスで必ず20時間分働くことを指示(強要)された時点で残業の強制に当たると考えられます。多くの企業で固定残業代の制度が採用されている中、正しい知識をもとに運用されていないケースも多々あるようです。
この際、残業代の取り扱いについて、雇用契約書及び就業規則にどのように記載されているかご確認をいただき、会社の上司や人事部と冷静に話し合いをされてはいかがでしょうか。また、同じ悩みをお持ちの同僚の方がいらっしゃれば一緒に話し合いをされることをお勧めします。
Q. 新たな勤務先(私立校)での就業が決まっているのですが、雇用の際の提出書類に【家族の学歴・勤務先及び地位】を記載する欄があります。保証人のサインも必要で、それは理解できるのですが学歴等まで提出する必要があるのかわかりません。そこまで家族の情報を開示したくないので、未記入で提出しても良いでしょうか。そもそもそのような情報を勤務校が求めることは問題ではないのかお聞きしたいです。採用面接の際にも「家族構成とその家族の職業を教えてください。」という質問もあり、違和感がありましたが、面接でしたので話せる範囲で伝えました。キリスト教の学校なので、家族の情報も必要なのでしょうか。
A. 採用面接時にも、家族の情報について質問されたとのこと、使用者が差別につながるような応募者の個人情報を収集することは、原則として認められていません。採用選考に当たり、「応募者の基本的人権を尊重すること」「応募者の適性・能力のみを基準として行うこと」が基本的な考え方として求められています。
求人・採用時に勤務先から家族の学歴など、応募者の適性・能力とは関係のない事項を確認されたことは、不適切であると考えます。採用後においては、原則収集する個人情報の目的・範囲を明示し、本人の同意があれば取得可能ですが、個人情報の収集の前提として「本人の同意」が必要です。キリスト教の学校であろうと、本人の確認なく、勤務先が家族の個人情報を得ようとすることは控えるべきだと考えます。
勤務先に家族の情報を求めることについて、その理由の説明を求められることをおすすめします。新たな採用先であり、申し出にくいお気持ちもお察しします。勤務先で問題が解決しない場合は、勤務地を管轄する労働基準監督署内の総合労働相談コーナーに相談してください。
Q. これまで知らない間に就業規則が変更されてきたが、今回初めて従業員代表が選出されました。しかし、その選出の仕方が会社主導だと推察されます。技能実習生に確認したところ「会社の○○に言われた」と言っています。また役員(部長:社長の弟)も従業員として加わっています。
A. 過半数代表者は民主的手続きで選出されることが必要です。過半数代表者は従業員全員に関わる重要な労使協定を締結するか、しないかについての判断をすることになり、総務部の課長、係長といった職務と代表の立場が両立できない人は代表者として選出すべきでない。(労基法施行規則第6条の2)と定められています。
選出方法は、投票(無記名・秘密投票)が原則ですが、挙手、起立、回覧などによる信任や、各職場代表者による互選も認められています。一方、使用者からの指名、親睦会の代表者や一定の役職者が自動的になる場合、一定の役職者の互選は違法となります。
過半数代表者の選出に問題があることについて、声を上げなければ会社の姿勢は変わりません。過半数組合があれば、労使協定の労働者側当事者になります。労働組合を立ち上げることをぜひ検討してください。
Q. 適応障害と診断され、当日欠勤が増えている状態です。2月はじめに診断書を会社へ提出したところ、月給の契約社員から日給のアルバイトへ契約変更する旨を伝えられました。会社は20日締めのため、前月の締め日まで遡って契約変更するとのことですが、新しい契約に関する書類をもらえていません。自分の契約が今どうなっているのか不安です。また、診断書提出の際に社長から「提出するな。自分で処分しろ。」と言われて対応が雑だったため、今後症状が悪化した場合、適切に対応してもらえるのか心配です。
A. 契約社員とのことですが有期契約の場合、雇用契約期間が満期になっていなければ、契約期間の途中でアルバイトへの変更は、本人の同意がない限りできません。新たな労働契約の条件や書類が無い中で同意する必要はありません。
雇用契約の終了日に次の雇用契約を締結するにあたり、会社側が契約社員としての雇用契約を拒む場合、アルバイトとしてでも働き続けたければ、次のアルバイトの雇用契約を結ぶことは可能です。「新しい契約に関する書類をもらえない」とありますが、新たな書類がもらえない中で、同意する必要はありません。
新たに雇用契約を結ぶ際には、必ず正式な労働条件通知書を要求してください。また、診断書を提出したところ、契約を変更すると言われたということも疑問がわくところです。更に毎月20日の締め日に合わせて、契約を前月の締め日まで遡って変更するという対応は、会社としてあるべき姿ではありません。まずは、勤務先の上司または総務や人事など労務を担当する部署と、しっかり話し合うことをお勧めします。もし勤務先の理解が得られず、現状の雇用契約が守られない場合、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署内の総合労働相談コーナーで相談することも検討してください。
Q. 現在BtoBで勤務しています。社内には私の入社後に設立された別のBtoCがあり、そちらの人手が足りなくなったとのことで、BtoBから交代制でBtoCでの勤務を命じられました。勤務時間や形態がこれまでと違い、了承はしていません。(BtoBはシフト休/8時~20時・BtoCは土日祝休/7時~21時)このような場合、了承せずとも会社都合で社員の勤務形態は勝手に変更が出来るのでしょうか?労働条件通知書は手元に残してあります。
A. 基本となるのは雇用契約書(労働条件通知書)の労働条件です。通知書には、①労働契約の期間に関する事項、②就業の場所および従事する業に関する事項、始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに終業時転換に関する事項、③賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切および支払いの時期並びに昇給に関する事項、④退職に関する事項が明示されなければなりません。
これは会社側と相談者が合意した雇用条件であり守られなければならず、簡単に逸脱は出来ません。一時的に、応援で行く場合でも期間、労働時間の扱いなど、本人の了解は必要だと思います。
また、対企業業務と対個人顧客業務では応答時間が異なり、勤務時間が長くなっていると思われますが、その部分の賃金などは支払われているのでしょうか。一度、お近くの労働局相談コーナーで考え方などお聞きになることをお勧めします。
Q. 3月31日に入社前研修があったのですが、研修部の方から、給料は4月1日分から支払われることになっているとの話がありました。入社前研修は参加が必須で、9時~18時(休憩1時間)の範囲で行われており、無給では労働基準法に違反しているのではないかと思い、相談しました。
A. 相談者の情報からすると、無給では問題ありと思われます。本来、入社前・雇用契約前に開催する研修会は、労働ではないので賃金を支払う必要はありません。
したがって「研修会受講は任意です。受講されなくても、入社に影響することはありません。この研修会には賃金を支払いません。」などと案内することが一般的です。また、会社が入社予定者に対して「入社前の研修を実施しますので、参加の場合には○○○円の日当を支払います」といった旨の申し込みを行い、入社予定者がそれに応じた場合、この個別の契約に基づいて、会社にはその約束の金額を支払う義務が生じます。
相談では、参加が必須とあります。よって、全員に強制されているこの研修は、労働時間と考えられます。就業規則や個別の契約に基づく支払い義務が無くとも、入社前の研修が労働基準法に定める「労働時間」に当たる場合、最低賃金以上を支払わなければなりません。
Q. 私の働いている認知症型グループホームは、利用者一人ひとりに担当職員が付きます。施設で必要な利用者の歯磨きや、歯ブラシ、マスクなどが無くなったら、担当職員が必ず購入しなくてはいけません。勤務時間外で立て替え購入し、後日事務員へ伝え精算してもらいます。昼間の勤務時間では買い物へ行く余裕もなく、休みの日やプライベートな時間に利用者の買い物をしている状況です。無給で休みの日買い物業務をしていると思っているのですが、どうなのでしょうか?
A. 労働基準法では「業務の指示を受けて行っている行為」はたとえ勤務時間外であっても「労働時間」とみなされる可能性があります。相談内容からすると「業務命令に基づく労働」と解釈できます。
「利用者の必需品を担当職員が責任を持って購入しなければならない」「通常の勤務時間中にそれを行う余裕がない」「買い物は休みの日やプライベートの時間に当たり前のように行われている」「購入したものは後日清算されている=業務として扱われている」という状態であれば、業務外の好意ではなく、正当な業務=労働と解釈できます。
立て替えや精算の実務が行われていることからしても、会社として必要な物品を相談者が代りに買っており「業務の一環」として買い物をしていると判断されます。よって、「買い物に行った時間」も労働時間とみなされ、労働の対価として賃金に反映されるものと推察されます。
まずは、施設側(経営側)と、同じようにお考えの同僚の方と一緒に、各担当者が勤務時間内での購入が出来る仕組み(例えば「週に1度、買い物の時間を確保する」などの提案)や、施設、組織としてまとめて購入する体制など業務時間内で対応できるよう検討することについて、話し合うことをお勧めします。改善が行われない場合には、好意の一環ではなく、業務=労働時間(時間外)として把握してもらうことを確認されることをおすすめします。